“家庭医療”との出会い
副院長である私が、まだ学生だった頃の話です。
多くの医師が専門を選ぶとき、「どの臓器を診るか」「どんな病気を治すか」で診療科を決めることが一般的です。私も例外ではなく、学生時代はさまざまな実習を通じて自分に合う分野を探していました。
そんな中で出会ったのが、家庭医の先生たちです。当時、岡山県の大学に通っていた私は、北部の人口5,000人ほどの町にあるクリニックで実習をする機会を得ました。大学病院の実習とはまるで違い、驚きの連続でしたが、何より印象的だったのは、そこに関わるすべての人がいきいきと働いていたことです。医師もスタッフも、そして患者さんも、どこか温かく、楽しそうに見えました。
「自分もこんな場所で働いてみたい」
「こんなふうに関わりたい
――そんな気持ちが自然と湧き上がってきました。
大学に戻り、総合診療科の先生に相談すると、自分が見た医療は「家庭医療」と呼ばれ、それを専門とする医師を「家庭医」と呼ぶことを教えてもらいました。これが私と家庭医療との最初の出会いでした。








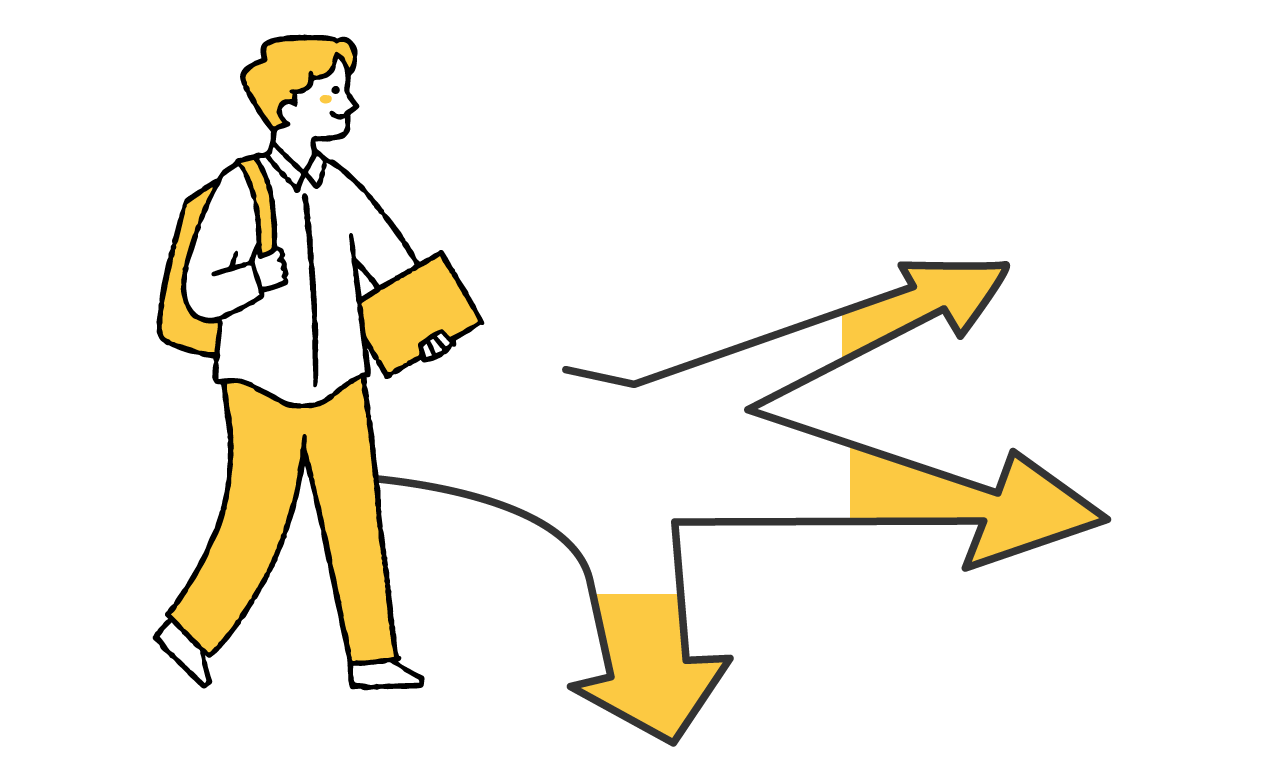

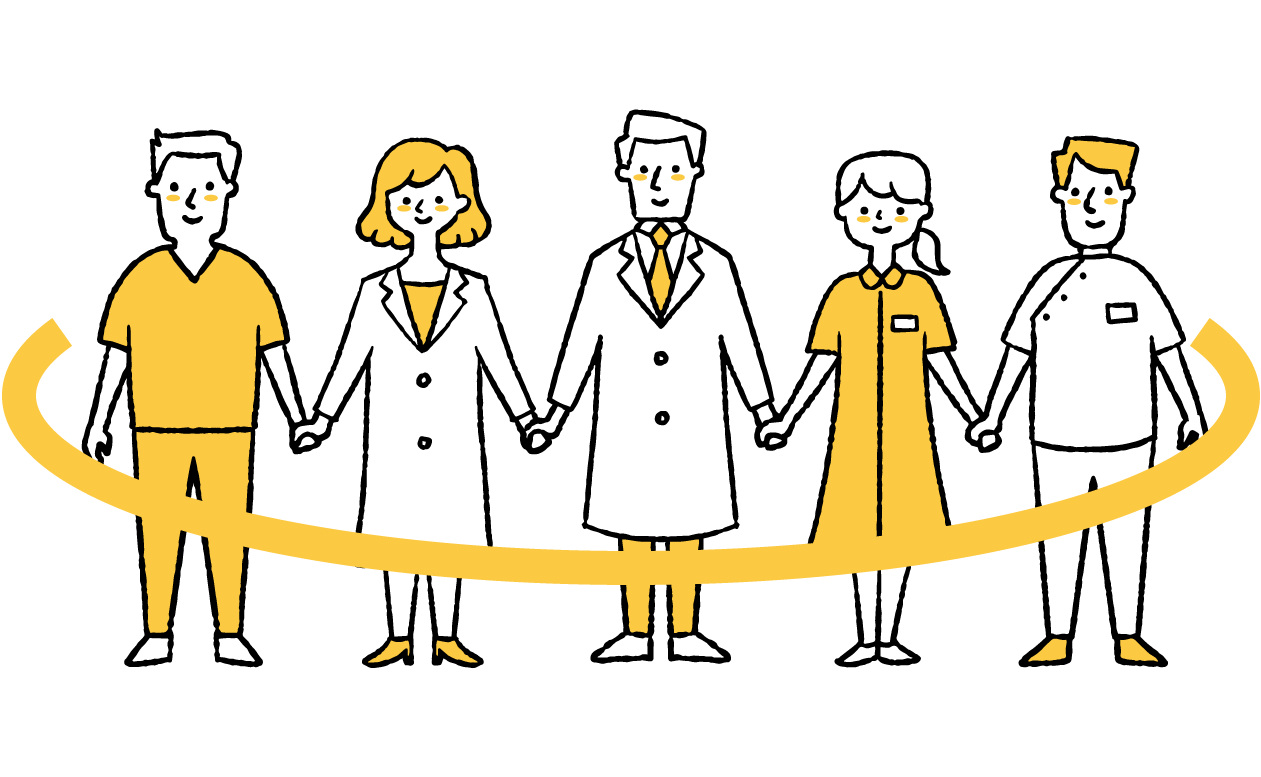



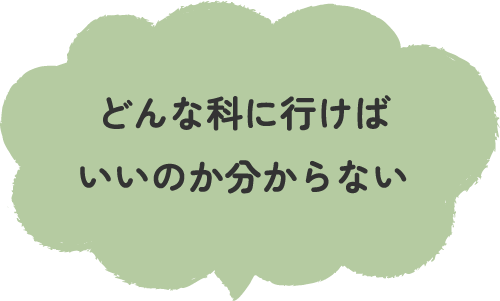
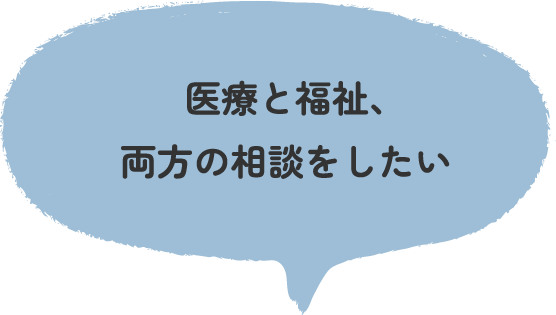
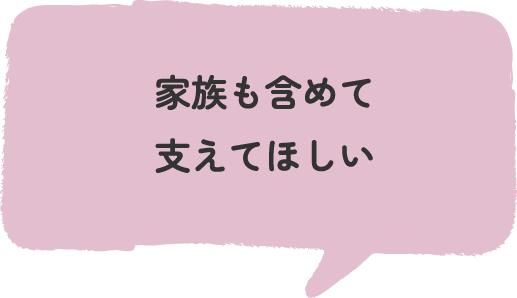
 森家が羽津の地で医業を始めたのは、室町時代末期、元亀年間と伝えられています。旧羽津病院の森家が「山の医者」と呼ばれていたのに対し、当院は古くから「町の医者」として親しまれてきました。
森家が羽津の地で医業を始めたのは、室町時代末期、元亀年間と伝えられています。旧羽津病院の森家が「山の医者」と呼ばれていたのに対し、当院は古くから「町の医者」として親しまれてきました。